アーツカウンシル前橋動画紹介「第8回文化芸術市民会議【文化国際課】
前橋文学館の改革コンセプト~これまでとこれから~
第8回アーツカウンシル前橋 文化芸術市民会議
リモート開催
日時:令和4年2月19日(土曜日)午後2時~
会場:前橋文学館ホール
「前橋文学館の改革コンセプト
~これまでとこれから~」
対談
前橋文学館 萩原朔美×アーツカウンシル前橋統括責任者 友岡邦之
(友岡統括責任者)
前橋文学館は、2016年に萩原朔美さんが館長になり劇的に変わった。「文学館」は博物館施設としては地味だったが、そういったイメージを打ち破った。当初の想いとはどんなものだったのですか。
(萩原館長)
・「文学館」なのに「ことば」を展示していないこと。私は、「文字」を展示した方が良いと提案し、壁に詩を表示した。
・声の展示をなぜしないのかと思い、紙の上の記号だけでなく音声(発生言語)によって人に伝えようと思い、リーディングを始めた。
・キャッチフレーズが弱くPRが下手だった。チラシは、デザイナーに頼みワクワクするようなチラシを作った。
・建物も威圧感があり威嚇的だった。文学館はそうではなく「どうぞ入ってください」という演出のため、外にカフェの黒板を出し、旗を外に飾り、低姿勢になった。市民と同じ立場に立ち、「一緒に作ろうよ」という気持ちを持つと、「教える」「教えられる」という関係ではなくなる。親しみのある文学館となる事が理想。
・文学館に来て、「こういう言葉を待っていたんだ。」と、言葉によって人生を豊かにしてもらう「言葉との出会い」があったら嬉しい。
(友岡統括責任者)
前橋文学館の展示は2階と3階で違う。2階は詩人の企画展、3階はポピュラーな漫画やイラストの展示だ。それは戦略的にそうしたのですか。
(萩原館長)
そうだ。どこもかしこも全部展示場だと問い直すと、廊下で素晴らしい作品との出会いが絶対にある。私は、文学館を建物だと思っていない。「文学館は出来事である。」前橋は「水と緑と詩のまち」なので、まちのあらゆる所で詩に出会えると良い。第一回の朔太郎賞を取った詩碑に「ことばの素顔を見てみたい」と彫ってあった。本当に見てみたいと思った。言葉が軽くなってしまった今だからこそ、文学館が役割を果たすべき。「本当の言葉の素顔」を文学館が見せなくてどこが見せるのか。
(友岡統括責任者)
今は朗読に向いている詩が増えてきたように思う。それは今の時代が養成しているのか。
(萩原館長)
そうかもしれない。朗読会が盛んに行われ、全国大会もある。詩人そのものが朗読したいという想いが溢れてきた。私も役者として「この詩をどうやって声に出そうか」と悩む事もある。 (友岡統括責任者)
多くの人が「詩」を軽視して遠ざけているのは、詩から“意味”を求めているからだという気がする。同時に、“詩は意味だけではない”と腑に落ちるまでが、多くの人にとって難しい。そこが、詩を多くの人が楽しめるかどうかの分水嶺になっているのか。
(萩原館長)
読むといいかもしれない。これは新鮮な出会いだった。
(友岡統括責任者)
言葉で書かれているのに、“意味”だけの問題じゃない。詩と散文の違いは、お芝居と舞踊の違いに似ていると思う。芝居ではストーリーという“意味”がついてまわるが、舞踏は“意味”を超えたところが全面に出て来る。
(萩原館長)
似ている。
(友岡統括責任者)
朔美館長はエッジの効いた「演劇実験室 天井桟敷」にかかわっていたと同時にポピュラーカルチャーの最前線にも関わっておられた。間違いなく、「ビックリハウス」のご経験が文学館を変えて行くときの感性に通じていると思う。「ビックリハウス」を立ち上げることになった経緯や、ターニングポイントになったような経緯があればお話しを伺いたい。
(萩原館長)
「ビックリハウス」をする前に、映像の作品をかなり作った。それをニューヨークへ持っていって上映したが、その時に“VillageVoice Media”というサブカルチャーの新聞に書いてもらった。それが嬉しくて、そういったアートの情報誌を自分で編集したいと思った。渋谷でラジオを放送していたパルコに企画を持っていったら「タウンマガジンをやるのだったらお前らがやれ。」と言われて始めた。素人3人で始め、「どうしよう。」ということで、「ぼくらはメインカルチャーを目指すのではなく、王道であるメディアを茶化して遊んでやろう」と、有名雑誌のパロディなどをやったらとてもウケた。読者の一番大きい“体制”は“コマーシャル”だと気が付いた。それで、笑いのめす対象を次々と変えて行った経験から「何が望まれているか」を読み取らないとウケないとその時思った。
(友岡統括責任者)
私もあの当時サブカルチャーに飢えていた。ある種の知性に飢えていている人達、水で薄められたメインストリームのカルチャーに満足できない人達が「ビックリハウス」のような裏路地のカルチャーに食いついたのだと思う。そこから80年代的なサブカルチャー、それに支えられたセゾンカルチャー、そういったものが成長した。「ビックリハウス」というメディアの果たした役割は大きい。そのメディアがあるからこそ、地方に住んでいて渋谷に行けない人達が食いついた。その存在は大きかったと改めて想い出す。
(萩原館長)
いろいろな人が関わってくれた。「おもしろい」と言っていただいたので、一つのブームを作ることが出来た。今はああいったことは難しい。
(友岡統括責任者)
今、あの手のものはインターネット上のSNSに流れたのだろうか。紙媒体の雑誌は生き残りが難しくなっている。
(萩原館長)
文学館も紙媒体を主にせざるを得なかったが、新しい作家は紙で書いていない。ほとんどパソコンで書いている。パソコンを資料に展示しても仕方ない。今後どうやって資料を展示するのかが文学館のテーマでもある。
(友岡統括責任者)
編集に携われた後、朔美さんはどのようにしてご自身の道を歩まれたのですか。
(萩原館長)
自分が何をしたいかという事は未だにわからない。去年、世田谷美術館に私の全作品が収蔵された。それで、「俺はアーティストになれた」と思った。担当学芸員が「朔美さんの作品は、文学館で展示されれば“朔太郎の孫”だけれど、ウチで収蔵されれば“朔太郎の孫”なんて関係ありません。“単なる現代美術の作家“として扱います。」と言われ、世田谷美術館から出て駅まで泣いた。私は表現者としていろいろやったが、「表現者として”朔太郎の孫“とは違うところで満足したかったのだ。」と、はっきりした。写真や動画を通じて、自分なりの表現をしたいことは確かだ。役者もしているのだが役者としての自分を絶対に続けたい。
(友岡統括責任者)
役者であることの醍醐味は何ですか。
(萩原館長)
決定的なことは、「私が無くなる」。これは日常ではできない。役者として台本を出されて、あるキャラクターを演じることは“私”ではない。“私”を捨てるより気持ちの良いものは無い。表現は「私!私!」と言い続ける事だと思うかもしれないが、とんでもない。表現は“私を無くすこと”だ。表現というのは、“私”という名前を世に知らしめて大きくすることではない。“私”の仕事を大量にやって“私”が完全に無くなるのが表現だ。 “私”が消えてしまうくらいの作品が出来れば素晴らしい。圧倒的な存在感によって、作家を超える。それがなかなか難しい。
(友岡統括責任者)
多様なジャンルにクリエーターとして関わっていらっしゃるわけだが、そのジャンルの違いは意識しているのか、たまたまそのジャンルにならざるを得なかった、という事なのですか。
(萩原館長)
多分、たまたまだ。祖父や母、友人がすごい人になってしまうので、自分は違う方向にと隙間を探しているうちに何も残らなかったという感じかもしれない。
(友岡統括責任者)
それでも、写真や映像表現、お芝居など自分の表現の場は見つけ出したということですか。
(萩原館長)
そうだ。今でも、“表現”として意識しているかどうか分からないが、何かしら作って外に出していないと不安だ。
(友岡統括責任者)
朔美館長のこれまでの取り組みの中には、エッジの効いたアートのハードコア的なものに関わり、その一方で、ごく敷居の低いポピュラーな物にも強い関心を持っていらっしゃる。そのバランスのとり方を意識している事はありますか。
(萩原館長)
全然意識していない。
(友岡統括責任者)
ポピュラーカルチャーとアートのハードコア的なものは一線上に並んでいるのですか。
(萩原館長)
区別したことが無い。ハイカルチャーとポピュラーが全く同一に並んでヒエラルキーは無い。
(友岡統括責任者)
そういったスタンスが前橋文学館に反映されているのでしょう。 朔美館長の今年の大きな仕事として「朔太郎大全」という企画があるが、概要についてご説明いただけますか。
(萩原館長)
・文学館は情報発信が弱い。そのために何か企画がないかと思い、「日本に52ある文学館が一斉に萩原朔太郎をテーマにして企画展を始めたらどうなるか。」と考えた。
・一人の詩人の業績だけでなく、言葉の軽くなった時代にもう一回言葉の素晴らしさを再確認するために企画した。
・詩人が「言葉を目的としてどういう姿勢で、どういう考え方でどう表現領域を広げたか」ということを、もう一回検証してみる機会があれば、言葉の再認識があるのではないか、言葉の軽くなった時代に一番重要な事ではないかと思い、朔太郎大全を起想した。
・必ずしも一人の、「萩原朔太郎」という固有名詞のことではなくて、“朔太郎”という、「今まで使われていなかった言葉、表現を使って、これまでの表現を一切変えてしまうような、或いは、言葉の表現の領域を広げる役割を果たしているもの」を、もう一回考えてみようと思った。
・令和4年10月に開催されるが、文学館には資料が全て無くなる。その空になった文学館をテーマにして何をするか。
・それぞれがそれぞれのテーマでいろんなアプローチをしていただければ面白い。私達は朔太郎をテーマにしたリーディングポエムを企画している。できれば全国を回りたい。
(友岡統括責任者)
「詩においては、言葉は意味を超える」とおっしゃったが、それを革命的にもたらしたのが朔太郎だった。「おわぁ、こんばんは」という言葉で、何かとんでもない衝撃をもたらすことはめったにない。それがこの機に全国で展開されるとは、画期的な年になりそうだ。朔美館長の作品が世田谷美術館に収蔵されたのは去年、この1、2年がご自身にとってもターニングポイントになっているのですか
(萩原館長)
令和4年12月から作品展が始まる。まさか自分の作品が美術館で展示される時が来るとは思わなかった。
(友岡統括責任者)
“萩原朔美”という人物が形成される中で、ご家族ご親戚との関係があったと思う。“アーティスト・萩原朔美”が誕生するにはお母さま(萩原葉子・小説家)の存在も大きい。「萩原葉子展」を拝見したが、お母さまにまつわる朔美館長のインタビューがあり、朔美館長が会社を立ち上げた時、「あなたが堤清二(実業家・小説家・詩人)になれるわけがない」、朔美館長が大学に就任する時も「そんなのは、あなたの仕事じゃない。」とおっしゃった。続けて朔美館長がおっしゃっていたのは、「自分の母親は“仕事”と“お金を稼ぐ”事を結び付けて考えてはいなかった。」と。朔美館長が育った環境の中では価値観に関して、ごく一般的なものに対しては違うものをぶつけられてお育ちなのかと思う。それについて、ご自身の環境認識はあったのですか。
(萩原館長)
ありました。やはり、大きい。「私は、表現者にならなければこの人に一生認められない。」と本当に、つくづく思う。大学教授になっても、彼女は何の興味もない。版画を作って東京国際ビエンナーレで賞を取ったのだが、ものすごく喜んだ。寺山修司さんの「演劇実験室」に入った時も喜んで毎日観に来た。ブラブラとしていても、一回も「勤めろ」とは言わなかった。「一生人に使われる身なの?楽しいの?」と言われる。そう言われれば、「楽しくないだろう。」と。それで3人で会社をやった。「ビックリハウス」の時は楽しかった。私はお金儲けが楽しいのだが、母はほんとうに嫌がった。「忙しそうにしているけど何の意味もない」と。でも、私は本当に楽しかった。文学館で企画をする時は、そのパルコにいた経験から「いかにお祭りをやって人を呼ぶか」その提案をしなければならない。増田通二さん(パルコ元会長)の発想は厳しくて、相当面白いことを言わないと怒られる。ただし、面白い事を言うと、僕らのような若造に予算を平気で出す。それ以外一切文句を言わない。その決裁の素晴らしさ、上に立つものは相手の才能を認めて、決意したら絶対に任せる。そういう意味では、上に立つものは「相手の面白いところをいかに引き出すか」がテーマだ。文学館の企画も私が増田通二の役割を果たして、面白い事を言ったらその人を自由にして認める。
(友岡統括責任者)
勉強になる。組織とクリエイティブの関係は大きな課題だ。前橋市の文化行政にとっても。役所というのは組織の中でも硬直化している所がある。その行政がクリエイティブに関わる時には、どういうスタンスが必要なのかと考えてしまう。
(萩原館長)
役所にいると、「前年やったことが素晴らしい」というのだけれど、私は前年やったことはやらない。「昔、成功した。だから、やらない」新しい事をやらないと、仕事は面白くない。そういう意味では、前橋市がアーツ前橋と文学館を直営するのだとすると、今までの市の考え方、行政マンの考え方を一切否定しなければ新しく前に進まない。前年と同じことを一切やらないということ。完全に追い込まれた状況からクリエイティブは始まると思う。
(友岡統括責任者)
必死の勢いで頑張った果てに何か新しいクリエイティビティが生まれる。そういうものに朔美館長が関わって来られたのは、お母さまやご親族の関係もあったと思う。アーツカウンシル前橋に携わる人間としては、「より多くの市民がクリエイティブなものに触れる生活を送れるようになってくれたら」という想いもある。しかし、誰もが芸術一家に生まれるわけでもなく、知り合いに芸術家がいるわけではない。それでも、「単に芸術作品を見る」だけでなく、その芸術作品を生み出すような人と身近に触れ合える機会があれば、「クリエイティブに生きるとはこういうことなのか。」と実感できる気がする。そういった機会づくりを何かできないかと思いこの仕事に関わっている。今までのご経験の中で、芸術に深く関わって来なかった方が表現に携わる人と出会うことで変わった事例はありますか。
(萩原館長)
私は読書が嫌いで全然本を読んでいなかったのだが、なぜ24歳で文章を書けたかというと、子どもの時に叔母が文学全集を全部読んでくれた。そのリズムを覚えていたから書けた。その経験があるので、文学館で幼稚園を回って読み聞かせをやっている。コロナで2年やっていないが、それは文学館の役割。大人の役割。
(友岡統括責任者)
多くの前橋市の皆さんにもそういう経験をしてもらえる状況を何とか作り出して行きたい。
(萩原館長)
絵画の場合は完成されたものでプロセスではない。そこに作家の筆の動きを見ることはできない。しかし、画家が絵画を見ると「この作者は左利きだな」とわかる。この絵をどこから書き始めて、どこに何を書いているのかが分かる発想を、絵を描かない人も味わえる瞬間がある。それは何かというと、作家の画廊を訪ねること。作家の仕事を観客として訪ねて、現場に立ち会えれば良い。完成品としてありがたく観るのではなく、「どこから作っているのか」くらいが分かると、作品が全く違うものに見える。そういう機会を作っていただけたらありがたい。
(友岡統括責任者)
これからの益々のご活躍を楽しみにしております。
(萩原館長)
ありがとうございました。
(友岡統括責任者)
我々の仕事はリサーチ業務等、比較的地味な仕事で表に出る事は基本的に無いが、縁の下の力持ちとしての役割を担うつもりで芸術文化と行政と皆様とアーティストの間を繋ぐための仕掛けづくりを今後も続けて行きたいと思っております。
この記事に関する
お問い合わせ先
文化スポーツ観光部 文化国際課
電話:027-898-6522 ファクス:027-243-5173
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから





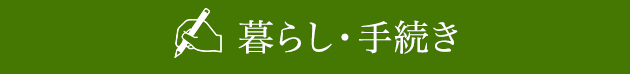







更新日:2022年03月16日