食中毒の原因(ボツリヌス菌)
ボツリヌス菌
ボツリヌス菌は、土壌に広く分布しており、海や湖の泥の中にも存在している嫌気性菌で、熱に強い芽胞を形成します。芽胞は、びん詰、缶詰、真空包装食品など、酸素が含まれない食品中で、発芽・増殖し毒素を産生します。芽胞を形成すると、120度4分間(あるいは100度6時間)以上の加熱をしなければ完全に死滅しません。
ボツリヌス症について
ボツリヌス症は、食品中でボツリヌス菌が増えたときに産生されたボツリヌス毒素を食品とともに摂取したことにより発生するボツリヌス食中毒と、乳児に発生する乳児ボツリヌス症等に分類されます。
ボツリヌス食中毒
ボツリヌス食中毒は、ボツリヌス毒素が産生された食品を摂取後、感染してからおよそ8時間~36時間後に、吐き気、嘔吐、下痢などの消化器症状、視力障害、言語障害、嚥下障害などの神経症状が現れるのが特徴で、症状が進むと、物が二重に見えたりまぶたが下がったり、言葉が出にくくなります。さらに進行すると呼吸困難を引き起こして死亡することがあります。
乳児ボツリヌス症
乳児ボツリヌス症は、1歳未満の乳児にみられるボツリヌス症です。ボツリヌス菌が食品などを介して口から体内にはいると、大人の腸ではボツリヌス菌が他の腸内細菌との競争に負けてしまうため、通常、何も起こりませんが、1歳未満の乳児の場合、まだ腸内環境が整っておらず、ボツリヌス菌が腸内で増えて毒素を出します。 乳児では、ボツリヌス菌の芽胞を摂取すると腸管内で菌が増殖し、産生された毒素が吸収されてボツリヌス菌による症状を起こすことがあります。症状は、便秘状態が数日間続き、全身の筋力が低下する脱力状態になり、哺乳力の低下、泣き声が小さくなる等、筋肉が弛緩することによる麻痺症状が特徴です。
主な原因食品
保存食品・発酵食品である、いずし、魚のくん製、缶詰、びん詰、自家製の野菜・果物の缶詰、真空包装食品などで、自家製の海産物や、保存状態の悪いびん詰などが原因食品として挙げられます。
乳児ボツリヌス症については、はちみつが原因食品としてあげられますが、自家製野菜スープが原因と推定された事例や井戸水が感染源と推定された事例も報告されています。

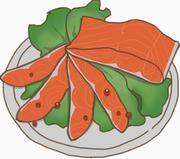
予防・対策
ボツリヌス食中毒
喫食前に十分な加熱(80度30分間の加熱処理等)を行うことで、食中毒症状の直接の原因であるボツリヌス毒素は失活するので効果的です。缶詰・瓶詰及び真空パック食品などの容器包装詰食品では、異常膨張又は異臭がある場合には喫食しないで廃棄しましょう。
乳児ボツリヌス症
1歳未満の乳児には、ボツリヌス菌の芽胞に汚染されている可能性のある食品(はちみつ、はちみつ入りの飲料・お菓子など)は与えないようにしましょう。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから












更新日:2020年10月07日